

カビ部屋になっていない?カビを除去して、カビが嫌いな部屋を作ろう!

「部屋がなんとなくカビ臭い」
「部屋の壁にカビが生えてしまった」
こんな悩みを抱えていませんか?
あなたの部屋は「カビに好かれる部屋」になってしまっているかもしれません。
カビに好かれる部屋で暮らしていると、アレルギーを引き起こしたり、肺炎などの病気になってしまうことも。
そんなことにならないためにも、本記事では以下についてまとめています。
【お部屋のカビについて】
・部屋のカビの原因
・カビの好む部屋
・部屋にいるカビの種類
・部屋のカビの落とし方
この記事を読めば、あなたの部屋をカビが嫌いな部屋にして、カビに悩まされることなく快適な生活が送れるようになりますよ!

部屋のカビの原因

カビは空気中に漂っています。
環境さえ整えばどこででも繁殖ができるので、気がついたら部屋のあちこちにカビが生えていた…なんて事も。
ここでは、部屋にカビが生える主な原因について説明します。
じめじめ高い湿度
カビは湿度が高いところに発生しやすく、逆に湿度が低いとカビの繁殖はストップします。
カビは、湿度が60%を超えると少しずつ繁殖し始めます。
湿度が上がれば上がる程、繁殖のスピードは速くなり、80%を超えると数週間でカビが発生してしまいます。
梅雨の時期などは特に湿度が高くなりやすく、気がついたら部屋のあちこちにカビが発生していた!なんて事も起こります。
部屋の湿度が60%以下でも、カビが発生してしまう事があります。
部屋の湿度は一定ではありません。部屋の真ん中と、隅の方では湿度に差があります。また、家具の裏側やベッドの下、クローゼットの中などは空気の流れが悪いため、湿気が溜まりやすくカビが繁殖しやすい環境になってしまっています。
暖かくなってきたら要注意。高い温度
カビは菌類です。菌類にはたくさんの種類があり、通常0℃〜40℃で生育します。
その中でも特に20℃〜30℃は、カビにとって最も快適で繁殖しやすい環境です。
日本には四季があるため、梅雨の時期から夏はどうしても室内温度も高くなり、カビが繁殖しやすくなってしまいます。
栄養が豊富
カビも生きているので、食べ物がないと繁殖することができません。
カビは家の中にある様々な物質を栄養としてつかう事ができます。ホコリや食べカス、人間のアカなどはカビにとってはご馳走です。掃除をサボったりしていると、カビは栄養をどんどん吸収し繁殖してしまいます。
また、カビはフィルターにも繁殖します。通気孔やエアコンのフィルターは空気を循環させる際、空気中のホコリやゴミなども一緒にフィルターに付着してしまいます。その汚れやホコリをそのままにしておくと、カビが繁殖します。
カビの好む部屋

カビが好む部屋、生えやすい部屋には特徴があります。
カビが生えやすい部屋の特徴を知っておけば、賃貸でその部屋を借りなくて済みますし、家の中でカビが生えやすい部屋があるのなら、適切な対策をとる事ができます。
カビが生えやすい部屋の特徴は以下の通りです。
【カビが生えやすい部屋の特徴】
・日当たりが悪い
・鉄筋コンクリート造
・部屋が1階
・物が多い
この5つの特徴を理解して、きちんと対策をしていきましょう。
日当たりが悪い
日当たりが良いと、太陽の光で部屋の中も乾いた状態にしてくれます。
しかし、北向きの部屋や、窓が少なく風通しの悪い部屋では、太陽の光が部屋に入ってこないため湿気が溜まりやすくなります。自然に湿気を取り除く事も難しいため、カビが繁殖しやすい環境になってしまうのです。
鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造の建物は、金属が含まれているため外の熱を中に伝えやすいという特徴があります。これにより、結露が発生しやすくなります。結露が発生すると多湿な状態になることから、カビが発生しやすい部屋になってしまうのです。
また、木造と比べるとコンクリートには木材がもつ湿度調整機能がなく、室内に湿気が溜まりやすいため余計にカビが発生する原因になります。
部屋が1階
アパートやマンションの1階は、物理的に地面からの距離が近いため、地面から上がる湿気の影響を受けやすくなります。
特に雨が降った後などは水気が上がりやすく、地面に特に近い玄関などに湿気が溜まります。
また、1階は周辺の道路などから部屋の中が見えやすいため、窓を開けて換気したり、カーテンを開けて太陽の光を入れたりすることが難しく、湿気が溜まりやすい部屋になってしまいます。
物が多い
部屋にタンスなどの家具がたくさんある。
本が多く、床に重ねて置いてある。
物が多く部屋がごちゃごちゃしている。
こういった「物が多い部屋」は、カビが発生しやすくなります。
タンスなどの大型の家具が多いと、その後ろに湿気やゴミが溜まりやすくなります。
本は紙でできているので、湿気を溜めやすく、それが重ねて置いてあると更に換気が悪くなります。
物が多いということは、部屋に空気が溜まる場所が多くなり、湿気も高くなります。換気が悪く、ゴミやホコリも溜まりやすいので、カビにとっては居心地の良い部屋になってしまいます。
部屋にいるカビの種類

一言で「カビ」と言っても、カビには様々な種類があります。
その中でも、一般的に部屋に生えるカビは3種類あり、それぞれ特徴があります。
ここでは、「黒カビ」「青カビ」「赤カビ」について紹介していきます。
黒カビ
黒カビの特徴は、胞子が非常に軽く、どこにでもいる菌と考えて良いところです。
そして、他の種類のカビとは異なり、付着した素材に対して深く根を張ります。なので、表面の見えるところだけ黒カビを取り除いても、根が残っているため、再度発生する事が多いカビです。
壁やエアコンのフィルター、洗濯機や浴室など、どこにでも発生します。
青カビ
青カビは自然環境の中の様々な場所に存在します。
土や植物にくっついています。そのカビの胞子が風などに運ばれ、至る所に飛んで行くので、空気中にも多く存在しています。
青カビを生える場所で代表的なのは食材です。
餅やパン、みかんやりんごなど、食品に生える物は青カビである事がほとんどです。
青カビは人間の生活にも大きく役に立っているカビです。
抗生物質のペニシリンとして使用されたり、チーズに付着してブルーチーズとして楽しまれています。
カビがついている食材を食べると毒性がありますが、ブルーチーズに付着しているカビは青カビの中でも毒性のないカビの種類が使われ、その製造過程でカビの持つ有毒性を分解しているため、食べる事ができるのです。
赤カビ
赤カビは、湿度の多いところに発生しやすい特徴があります。
主に浴室に生えるピンク色のカビは赤カビです。
赤カビは栄養を必要とせず、「水のみ」で増殖します。
そして、洗剤に対しても耐性があるため、掃除をしていてもすぐに発生してしまう厄介なカビです。
しっかり掃除をしているつもりでも、シャンプーボトルの下や浴室のドアの隙間などに大量に繁殖していた。なんて事も起こります。
湿気が多いところであればどこにでも生える繁殖力の強いカビです。
部屋のカビを放置しておくとどうなる?

カビは、成長すると胞子を飛ばし更に繁殖します。
このカビの出した胞子を人間が吸い込んでしまうと、身体に様々な悪影響を及ぼします。
アレルギーの原因に
カビを吸い込むことで、アレルギー症状を起こしてしまいます。
主な症状は、かゆみ、湿疹、咳、鼻炎、結膜炎、呼吸困難などの気管支の症状があらわれます。
お風呂場に行くとくしゃみが出たり、エアコンをつけると咳や鼻水が出る。といった症状がある場合は、カビによるアレルギー反応の可能性が高くなります。
カビによるアレルギー症状は、梅雨時期から秋にかけて、高温多湿の環境で急増します。
病気の原因になる
カビの胞子に対して敏感に反応してしまい、咳が出る「夏型過敏性肺炎」という病気があります。
主な症状としては、咳、発熱、息切れで、「トリコスポロン・クタネウム」というカビが原因になって引き起こされるアレルギー疾患の一つです。このカビは6月から10月にかけて高温多湿な家の中に繁殖します。
このカビを繰り返し吸収することで肺炎を引き起こします。
また、家で過ごす時間の長い専業主婦などの発症率が高いこともわかっています。
部屋のカビの落とし方

気をつけていたのにカビが生えてしまった。どうやったら簡単にカビが除去できるだろう。と考えたことがあるかと思います。
ここでは、専門的な薬剤などを使わず、身近なもので効果的にカビを除去する方法について紹介します。
身近なアイテムでカビ落とし
・中性洗剤
中性洗剤は、軽いカビであれば除去する事ができます。
使い方は、中性洗剤を水で薄めたものを布に染み込ませ、カビを拭き取ります。拭き取れない場合は布をカビに押し当てたまま、5分程つけておくと、カビが取れやすくなります。
・塩素系漂白剤
塩素系漂白剤は黒カビに効果的です。
塩素系漂白剤は強力なため、色落ちの気になる素材や畳などの自然素材には使用できませんが、お風呂場などに発生した根が深い黒カビを落とす時には活躍します。
また、強力な分注意が必要で、使用する際には換気をきちんとして、有毒ガスが出るので酸性の洗剤と混ぜない事が大切です。
使用法は、カビに直接スプレーして数分おき、しっかり流水ですすぎます。
・消毒用エタノール
消毒用エタノールは、強い洗剤が使えない場所にも使用する事ができます。
カビを消毒するには、エタノール成分が70%以上のものが効果的です。
消毒用エタノールでカビを退治するには、布などにエタノールを染み込ませたものでカビを拭き取ります。
しかし、黒カビなどによってできたシミ汚れは取ることができません。
奥まで根が張る前に、こまめにカビ退治をする必要があります。
間違ったカビ掃除は危険
カビ掃除で気をつけたいのが「拭き掃除」と「掃除機」です。
カビは拭き掃除では退治できないうえ、表面を拭くことでカビを引き伸ばし、カビの範囲を広げてしまうことになります。
掃除機は、表面のカビは吸い込めたように見えても、根元まで吸引することはできません。
また、掃除機で吸引することで、掃除機の中にカビが発生してしまうことにもなりかねません。
こうなると、掃除機を使用する度に、排気に乗せてカビの胞子を部屋中に撒き散らすことになってしまいます。
部屋のカビを正しく掃除する方法

お部屋のカビはどのような方法で取り除けるのでしょうか?部屋のカビを正しく掃除する方法は以下の通りです。
【部屋のカビを正しく掃除する方法】
①しっかり換気を行う
②カビ部分だけでなく部屋全体を掃除する
③カビ取り剤はカビ部分にのみ使用する
④十分に乾燥させる
①しっかり換気を行う
正しいカビの掃除方法1つめには、しっかり換気を行うことが挙げられます。なぜなら、カビ掃除をしている最中にカビの胞子やホコリが舞ってしまう場合があるからです。カビの胞子を吸い込まないためにも、しっかりと換気を行いましょう。また、カビ取り剤には臭いがきついものもあるため、きちんと換気を行うことが大切です。必要であればマスクや手袋を装着して掃除を行いましょう。
②カビ部分だけでなく部屋全体を掃除する
カビが生えている部分はもちろん部屋全体の掃除も行うのが理想的です。今はカビが生えていない箇所にも、カビの胞子が付着している可能性があります。また、カビの餌となるホコリが溜まっていると、またカビが発生します。今後のカビを予防するためにも一度部屋全体を掃除するのがおすすめです。
③カビ取り剤はカビ部分にのみ使用する
カビ取り剤を使用する場合には、カビが生えている部分のみに塗布することが大切です。カビが生えていない箇所にカビ取り剤を使用すると、素材が傷んだり色落ちしたりする可能性も…。カビ取り剤の説明書きをよく読み正しく使用しましょう。
④十分に乾燥させる
カビ掃除が終わったら、しっかりと水分を乾燥させましょう。じめじめしたまま放置するとまたカビが発生する可能性があります。カビ掃除が終わったら風通しをよくし、できるだけ早く乾いた状態にするのがおすすめです。
部屋のカビ予防には【炭八】の使用がおすすめ
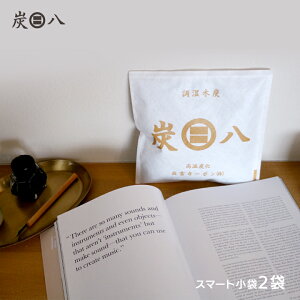
部屋のカビを予防するためには、調湿剤【炭八】の使用がおすすめです。炭八は部屋の湿気を吸ったり吐いたりすることで、常に快適な湿度に保ってくれます。部屋がジメジメした状態になるのを防げるため部屋のカビを予防したい方に最適です。半永久的に使用できるためコスパもよく、気軽に使用できます。

正しくカビに対処しよう!
カビはどこにでも存在し、環境が整えば、部屋の中のどこにでも生えます。
一度カビが生えてしまうととても厄介なカビ。カビの特徴を理解し、カビが嫌いな環境を作って、上手にカビを除去していきましょう。

古い家のカビ臭さが気になる方は「古い家がカビ臭い?!カビの臭い対策やおすすめのアイテムを紹介!」もチェックしてみてくださいね!
著者情報

最新の投稿
 カビ2021.12.20カビスプレーの種類と効果的な使い方!おすすめ商品を紹介!
カビ2021.12.20カビスプレーの種類と効果的な使い方!おすすめ商品を紹介! カビ2021.12.09カビ取りジェルでしつこいカビを落とそう!
カビ2021.12.09カビ取りジェルでしつこいカビを落とそう! カビ2021.11.29私たちにとって身近なカビの種類と特徴について解説
カビ2021.11.29私たちにとって身近なカビの種類と特徴について解説 カビ2021.11.06気がついたらカビだらけ!?フローリングマットの下の畳にカビを発生させない方法を紹介
カビ2021.11.06気がついたらカビだらけ!?フローリングマットの下の畳にカビを発生させない方法を紹介










この記事へのコメントはありません。